唐辛子は、ほとんど手入れもいらず、
簡単に栽培できる野菜なので、
初心者におすすめです。
辛味の成分はカプサイシンで、
消化をよくし、食欲を増進させ、
血行をよくする働きがあります。
そこで今回は、
唐辛子の育て方について
上手に美味しく育てるコツを紹介します。
スポンサードリンク
唐辛子の品種について
鷹の爪
長さ3~5cmの実が上向きに付く様子が、
鷹の爪を思わせることから名前が付けられた唐辛子の品種です。
真っ赤に熟した実を生や乾燥させ、
様々な料理に利用します。
また、一味の原料でもあります。
育てやすく、日本でも盛んに栽培されています。
⇒鷹の爪
ハバネロ
超激辛唐辛子として世界的に知られる品種で、
猛烈な辛さの中にフルーティな香りがあるのが特徴です。
実は2~6cmほどで、丸みがあり、
オレンジ色をしています。
日本ではお菓子に使われたことで知られるようになり、
激辛ブームの火付け役となりました。
⇒ハバネロ
唐辛子の育て方について
過去に唐辛子と同じナス科の植物を植えた土を使わない、
日当たりのよい場所に植える、
支柱を立てることの3点が栽培のポイントです。
ナス科の植物を育てた土を使うと、
害虫や養分不足によって生育が悪くなる連作障害が引き起こされます。
また、日当たりが足りないと花が咲きづらく、
実がつきにくくなってしまいます。
さらに、根が浅く、株が倒れやすいので、
支柱を立てて支えてあげると安心です。
唐辛子の種まきの仕方について
使用する道具
育苗箱に、
4~5cm間隔で浅い溝を作り一列に種を蒔く、
条まき(すじまき)をします。
覆土は1cmくらいです。
28~30℃くらいに保温します。
用土は、種まき専用の培土を使用します。
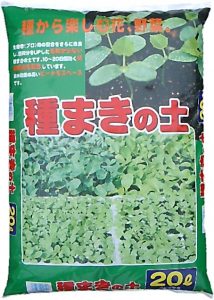
本葉が1枚のころ、4号ポットに植え替えます。
夜間の気温が、15℃以下にならないように保温してください。
花が1~2個、開花するまで育苗します。
大苗にして、じゅうぶん暖かくなってから畑に植えつけます。
発芽したばかりの唐辛子苗は、
以下のような形をしています。
土づくりについて
使用する道具
日当たりがよい場所を選んで、
植え付ける2週間前から土作りをしていきます。
まずは、耕した土1㎡あたり両手いっぱい(100~150g)の苦土石灰を加えて、
よく混ぜあわせます。
そして、1週間寝かせたら腐葉土や堆肥、
油かすなどを混ぜてさらに1週間寝かせた後に植え付けていきます。
土の水はけが悪いようなら、高さ10~15cm、
幅40~60cmの畝を作ってもよいですよ。
株同士の間隔は30cm空けるようにします。
土壌のpHは6.0~6.5が適しています。
酸性に偏っていれば、
苦土石灰をまきます。
土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。
スポンサードリンク
唐辛子の肥料の与え方について
使用する道具
唐辛子は、茎葉を伸ばしながら次々と実をつけていくので、
栽培期間を通じて肥料切れを起こさせないように、
定期的に追肥します。
初期からリン酸を効かせることで、
実付きがよくなります。
肥料には、化成肥料や配合肥料・液肥などがお勧めです。
液肥の場合は、
1番果を収穫した時に、追肥を始めます。
1週間に1回、500倍に薄めた液体肥料を、
水やり代わりに施します。
次々に実がつくので、
疲労させないように追肥を忘れないように施しましょう。
プロも愛用の人気植物活力液!
全ての植物にオススメ。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」
唐辛子苗を整枝・誘引します
1番果がついて肥大し始める頃、
わき芽がのびてきます。
主枝と勢いよくのびるわき芽2本を残し、
それより下からのびるわき芽は全て取り除いて、
「3本仕立て」にします。
このとき、長さ150cmの支柱を2本を60度の角度でX型立て、
それぞれの枝をしっかりと結び留めて誘引しましょう。
生長とともに枝が込み合ってきたら、適宜枝を剪定します。
唐辛子を収穫しましょう
緑色の未熟果も食用として利用できますが、
辛味が強いので注意してください。
赤く色づいたものから順次収穫していきましょう。
唐辛子の病害虫対策について
唐辛子の害虫対策について
使用する道具
アブラムシ
殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。
植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。
カメムシ
唐辛子の病気対策について
使用する道具
うどんこ病
まとめ
唐辛子を栽培するときの注意点として、
近くにシシトウを植えないことです。
近くにシシトウを植えてしまうと、
シシトウまでもが、唐辛子の様に辛くなってしまいます。
最後に
最後までご覧いただき、
有難うございます。
その他の野菜の育て方も、
紹介していますので、参考にしてみてください。



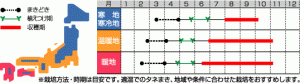



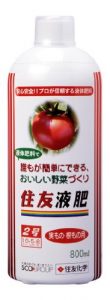






コメント