里芋は夏に収穫できる野菜で、
身がしまっていておいしいですよね。
里芋の栽培は手間はあまりかからず、
水さえあれば、
無農薬栽培や放任栽培にも向いています。
そこで今回は、
里芋の育て方について
上手に美味しく育てるコツを紹介します。
スポンサードリンク
里芋の品種について
土垂(どだれ)
土垂は、最もポピュラーな里芋の品種です。
土垂は主に関東地方で多く栽培され、
里芋=というくらい定着しています。
土垂は主に子いもを食用とする品種で、小ぶりの里芋です。
とは言うものの、農産物直売所などでは親イモも販売され、
地元消費されています。
子芋は煮ころがしに使われるように、
鍋の中でころころと転げるサイズです。
また、親イモは大きく、皮を剥く手間が少なくてすみます。
特有のぬめりがあり、
肉質もねばりがあり煮くずれしにくいのが特徴です。
晩生種で貯蔵性が高く、
一年中出回っています。
また収量性や栽培しやすいこともあり、
家庭菜園でも人気があります。
⇒土垂
石川早生(いしかわわせ)
石川早生は、土垂と並び
里芋の代表格です。
大阪府南河内郡の石川村(現河南町)がこの芋の原産地とされ、
その地名がつけられています。
またその名のとおり早生品種で、
宮崎県では7月から収穫が始まります。
子芋は他の品種に比べ小ぶりで、
煮物やきぬかつぎにされることが多いです。
8月15日、十五夜の月見はイモ名月とも言われ、
この石川早生を皮ごと蒸して塩を振って食べる習慣があります。
この料理を「きぬかつぎ」と呼びます。
また、秋に採れる石川早生の小さな子芋自体も、
キヌカツギと呼ばれたりします。
石川早生の子芋は蒸したり茹でると、
手で簡単につるっと皮がむけます。
肉質に粘りがあり、
蒸したときに皮離れがいい石川早生ならではの食べ方です。
⇒石川早生
八つ頭
ヤツガシラは流通している量が少なく、
里芋としては高価で、
末広がりの「八」と、
子孫繁栄や人の「頭」になるようにという
縁起物としておせち料理によく使われます。
子芋が分球しないため、
親子もろともひとつの塊になるタイプです。
その姿が、頭が八つ固まっているように見えることから、
ヤツガシラと名づけられ、「八頭」や「八つ頭」と書かれます。
ヤツガシラは、子イモがほとんど分球せず固まりになってしまうので、
全体に入り組んだ形をしているため、
皮を剥くのがとても面倒なサトイモです。
ごく僅かに分球した子イモ(孫イモ)ができ、
それは「八つ子」と呼ばれています。
肉質がしっかりしていて、
煮ると粘りが少なくほくほくした食感が楽しめ、
とても美味しいです。
栄養成分も一般的なサトイモに比べ沢山含まれています。
⇒八つ頭
セレベス
セレベスはインドネシアのセレベス島(現スラウェシ島)
から伝割ったとされる里芋で、
その島の名前がつけられています。
親子兼用品種で、子イモも大きく、
収量が多い事でも知られています。
芽が赤いのが特徴で、
赤芽芋又は赤目芋(アカメイモ)とも呼ばれています。
また、「大吉芋」とも呼ばれています。
⇒セレベス
里芋の育て方について
里芋は乾燥に弱く、
干ばつの年には不作で品質も悪くなることもあります。
特に夏の乾燥に弱いので、
水やりはこまめにやりましょう。
また、連作するとイモが腐りやすくなるから注意しよう。
土づくりについて
使用する道具
里芋の植え付け適期は、4月中旬~下旬です。
栽培期間がやや長く、葉が大きく茂り、
背丈も高くなるので、邪魔にならないように
植える場所を考えましょう。
連作を嫌い、同じ場所で続けて作ると、
センチュウなどの被害が出ることがあるので、
3年~4年(できれば5年以上)は里芋を育てていない場所を選びます。
また、里芋は地中深くへと根が伸びていくので、深めに耕しておきます。
種芋を植える2週間前までに、苦土石灰を入れて深く耕し、
植える1週間前に、化成肥料を1㎡当たり100g
を入れて深く耕し、畝を立てておきます。
里芋に適した土壌pH は6.0~6.5ですが、
4.1~9.1の範囲なら生育できます。
石灰を入れてpH調整しておきましょう。
土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。
種イモを植えていきます
あらかじめ準備しておいた畝に、
90cm幅であれば2列、間隔を40~50cmとし、
種芋の芽を上向きにして7~8cmの深さに植えます。
芽が露出していない場合、
ヒゲを分けてみると芽が見えます。
スポンサードリンク
土寄せと追肥をします
使用する道具
種芋の上に親芋がつき、
親芋を囲むように子芋がつきます。
なので、土寄せをしなければ、子芋が地表に露出し、
緑化して食味も形も悪くなり、芋の品質を著しく落とします。
よい子芋にするためには、
株の生育に合わせて少しずつ土寄せしつつ、
追肥を施すのがポイントです。
1回目は、葉が6枚になったころ、株間に化成肥料を施し、
10cmほどの高さの土を寄せます。
さらに2週間くらいたってから、
2回目の追肥と土寄せを施します。
土寄せのとき、
雑草をとってよく日が当たるようにします。
夏になると雑草の生育が旺盛になるので、
除草を怠らないように注意しましょう。
プロも愛用の人気植物活力液!
全ての植物にオススメ。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」
収穫まで、乾燥に注意しましょう
使用する道具
里芋は高温多湿を好み、気温が高くなると盛んに生育します。
しかし、乾燥には弱く、
気温の上がる6月から収穫期までの芋の肥大期には十分な水を必要とし、
土が乾くと芋の生育が悪くなります。
しっかりと、敷きわらで株元を覆って乾燥を防ぎ、
それでも土が乾くときは、7~10日くらいの間隔で、
朝や夕方に畝の間に潅水(水やり)をします。
潅水は、畝の中まで濡れるようにたっぷり行います。
大きく育ったら収穫します
収穫の時期は、
10月中旬〜11月上旬くらいです。
葉を根際で切り取り、
傷つけないようにサトイモの位置を確認してから、
親イモに子イモをつけたまま、
スコップで掘り起こし収穫します。
収穫は遅くても霜が降る前には掘るようにしましょう。
芋の保存の適温は7~10℃で、
5℃以下になると腐敗していき、
霜に数回あたると傷んで腐敗します。
親芋・子芋・孫芋について
里芋は、食べる部位によって種類が分けられ、
親芋用、子芋用、親子兼用があります。
子芋用が一般的で、中心の大きな親芋と、
それを囲むように子芋がつき、
さらにそのまわりに孫芋がつきます。
大きな親芋を中心に小芋、孫芋が増えていくことから、
子孫繁栄の象徴とされています。
里芋の病害虫対策について
里芋の害虫対策について
里芋は害虫に強く、
発生しても収穫にそれほど影響しないので、
とくに心配することもありませんが、
大型のイモムシのセスジスズメの幼虫や、
ヨトウムシが大量発生に注意します。
アブラムシやハダニが発生することがありますが、
よほどひどくない限り防除は必要ありません。
使用する道具
ヨトウムシ
アブラムシ

殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。
植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。
ハダニ
里芋の病気対策について
使用する農薬
モザイク病
汚斑病
まとめ
里芋を上手に育てるポイントは、
水を切らさない事と、
連作を避けることです。
連作をすると、病気にかかる確率が増えます。
連作と水に注意をすることによって、
害虫や病気の被害は心配することなく、
無農薬で育てることができますよ。
最後に
最後までご覧いただき、
有難うございます。
その他の野菜の育て方も、
紹介していますので、参考にしてみてください。





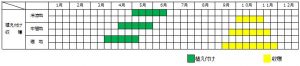

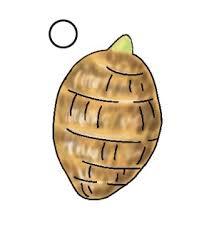


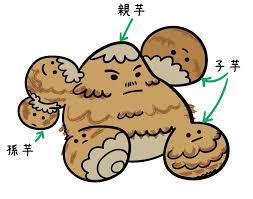






コメント