パセリは、料理の添え物のイメージが強いですが、
栄養価が高く、生活習慣病の予防や
胃腸の調子を整えてくれる効果があります。
パセリの香りや味が苦手な方もいるかもしれませんが、
栽培方法を工夫したり、
調理のときに熱を加えたりして苦味を減らこともできます。
そこで今回は、
今回は、パセリの育て方について
上手に美味しく育てるコツを紹介します。
スポンサードリンク
パセリに品種について
パラマウント
葉は濃緑色で縮みが細かく、
肉厚で、品質が特にすぐれます。
耐暑性にすぐれ、高温期にも平葉になりにくくて、
特に出回り量の多い冷涼地の夏秋どり栽培に適します。
イタリアンパセリ
セリ科の野菜で、日本で一般的に使われるパセリよりも、
葉が平べったく、風味・苦味・香りが
パセリよりも柔らかい特徴があります。
主にイタリア料理、
細かく刻んで料理のソースやドレッシングに利用されます。
パセリの育て方について
パセリは、水はけのよい土に植えて、
乾燥した後すぐに水やりをすることが上手に育てるポイントです。
乾燥に弱く、春~秋の生育期にかけては、
土に湿り気を保つようにしましょう。
また、収穫の際には1度にすべてを摘み取るのではなく、
10〜15枚ほど葉っぱを残しておくと、
何回も摘み取って楽しめますよ。
パセリの種を蒔きます
使用する道具
パセリは、4〜5月か9〜10月頃が種まきの適期で、
約70日で収穫できるようになります。
育苗ポットで苗まで育ててから植え付ける方法と、
直接鉢や地面に植え付ける方法の2通りがあります。
育苗するときは、
本葉が5~6枚になったタイミングで植え替えていきましょう。
直接土に種をまくときは、
管理が楽なプランターへ行うのがおすすめです。
発芽したばかりのパセリの苗は、
以下のような形をしています。
土づくりについて
使用する道具
パセリは真下に向かってまっすぐに根を張るので、
深めの鉢やプランターに植え付けます。
10号鉢な1~2株、
60cmプランターなら2~3株が植え付けの目安です。
容器の底に軽石と土を入れ、
株同士の間隔を15~20cm空けて植えていきましょう。
土は、赤玉土7〜8:腐葉土2〜3ほどの割合で混ぜたものか、
市販の花・野菜用の培養土を使います。
地植えの場合は、
酸性の土に弱いので、
植え付ける2週間前から土作りをはじめていきます。
畑の土1㎡あたりコップ1~1.5杯(100~150g)の苦土石灰を混ぜあわせます。
1週間ほど寝かせたら、
幅40~50cm、高さ10~15cmの畝を立てます。
畝の中心に深さ20~30cmの溝を堀り
溝を掘った土に堆肥、化成肥料、
油カスを混ぜあわせてから埋め戻します。
pHは6.0〜6.5が目安です。
石灰を入れてpH調整しておきましょう。
土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。
スポンサードリンク
パセリ苗を植えていきます
株同士の間隔が20~30cm空くよう、
植え穴を掘ってパセリの苗を植え付けます。
ジョウロでたっぷりとそれぞれの株に水を注ぎ、
畝全体にたっぷりと水をかけたら完了です。
パセリの肥料の与え方について
使用する道具
6〜7月頃の生育期は、
化成肥料を10~15日に1回、
液体肥料を7~10日に1回ほど施していきます。
順調に生長しているときは、
肥料を与えなくても大丈夫です。
鉢・プランターの場合は、
植え付けの土に市販の花・野菜用の土を利用していれば、
肥料の必要はありません。
プロも愛用の人気植物活力液!
全ての植物にオススメ。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」
適度に育ったら、収穫します
パセリの本葉が15枚以上になったら、
収穫のタイミングです。
必ず10〜15枚は葉っぱが残るようにして、
外側から使う分だけ摘み取っていきます。
内側の新芽は、
これから大きく育つところなので、
取らないように気をつけてください。
摘み取る際は、できるだけ根本から長く茎を摘み取りましょう。
爪の先やハサミを利用すると切り取りやすいですよ。
また、花が咲いてしまうと茎葉が固くなるので、
種を採取するとき以外は早めに摘み取りましょう。
パセリの病害虫対策について
パセリの害虫対策について
使用する道具
キアゲハの幼虫
アブラムシ

殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。
植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。
ネキリムシ
パセリの病気対策について
使用する農薬
立枯病
うどんこ病
まとめ
パセリは、香りを強くするには、
日にしっかりあてて、強めの肥料を与えます。
逆に半日陰で肥料を少なめにすると、
香りや苦味が弱くなります。
お好みに合わせて、
作り変えるのも家庭菜園だからこそできることですよね。
最後に
最後までご覧いただき、
有難うございます。
その他の野菜の育て方も、
紹介していますので、参考にしてみてください。

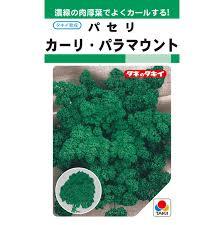
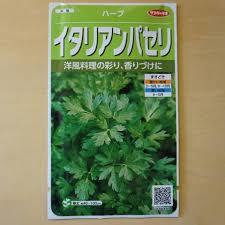
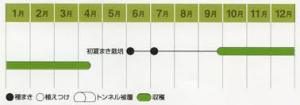








コメント